みなさんは、江戸幕府7代将軍について知っていますか。
この記事では、江戸幕府7代将軍徳川家継について紹介します。
江戸幕府7代将軍は誰?

江戸幕府7代将軍は、徳川家継です。
家継は、江戸幕府の歴代将軍の中で、史上最年少で征夷大将軍に任官され、史上最年少で死去しました。
徳川家継将軍になるまで
宝永6(1709)年7月3日、6代将軍・徳川家宣の四男として江戸城西ノ丸で生まれます。
母は側室・お喜世の方(月光院)で、幼名は鍋松といいます。
家宣の子どもはみんな病弱で、正室やその他側室の子どもはすべて早世し、鍋松だけが生き残りました。
正徳2(1712)年、家宣が病で倒れます。
原因は、インフルエンザだったと考えられています。
ところが、家宣の容態は一向に快癒せず、家宣は自分の死期を悟ります。
そこで、側近の新井白石と間部詮房を呼び、遺言を託しました。
新井白石の自叙伝「折たく柴の記」によれば、家宣は次期将軍について遺言で、2通りの考えを示しています。
- 後継者は徳川御三家の尾張藩主・徳川吉通とし、鍋松が成人してからのことは吉通に任せる
- 次期将軍は鍋松、吉通が後見役として政務を執り、もし鍋松が成人するまでに早世すれば、吉通が将軍を継ぐ
ところが、新井白石と間部詮房は、吉通を江戸に迎え入れることを避けようとしました。
理由は、吉通が江戸城に来れば、家宣の側近や江戸城の家臣は吉通が連れてきた家臣によって江戸城を追い出されると考えたからです。
しかし、それでは後見役を擁立しないまま、鍋松を将軍にする必要がありました。
このとき、鍋松はまだ数えで4歳(満3歳)、とても政務が取れる年齢ではありません。
幕臣の中には、万一鍋松の身に何かあって、世継ぎや後見役もいないまま早世してしまう最悪な状況を避けたいと言う者いました。
それに対して、新井白石はそのときこそ吉通を迎え入れるべきときだとして、幕臣達を説得、了承を得ました。
また、家宣が「鍋松が成人しなかった場合、吉通の子・五郎太か吉宗の嫡男・長福丸を養子にして、吉通か吉宗を後見役にさせよ」と遺言したともいわれています。
この年、正徳2年(1712)10月14日、家宣が51歳で死去しました。
史上最年少将軍の誕生

家宣が亡くなり、後見役もいないまま、鍋松がたった4歳で7代将軍に就任する運びになりました。
しかし、徳川将軍家の慣例で、次期将軍は父将軍から諱を受けて元服し、朝廷から大納言に任じられたあとに将軍を継ぐことになっていました。
ところが、家宣は鍋松の元服待たず、遺言を託すとすぐに亡くなったため、鍋松の烏帽子親を務める人がいませんでした。
そこで、幕府は霊元上皇に「名字書出」を申請することにしました。
「名字書出(みょうじのかきだし)」とは、烏帽子親が元服する子の諱を定める際、口頭で伝えたものを証拠として文書化したもののことです。
幕府の要請を受けた上皇は、12月12日に「家継」と名を記した宸翰(しんかん:天皇自筆の文書)を授けました。
かくして、家継は徳川将軍唯一の朝廷から諱を与えられた将軍となりました。
正徳2(1712)年12月25日、従二位権大納言に叙任、家継と名を改め、正徳3(1713)年3月25日、大老・井伊直該が烏帽子親になり、元服を行いました。
同年4月2日、家継は将軍宣下を受けて第7代将軍に就任しました。
家継は将軍に就任したとき、わずか4歳でしたが、「生来聡明にして、父家宣に似て仁慈の心あり。立居振舞いも閑雅なり」と「徳川實記」に記録されており、利発で心優しい少年でした。
新井白石から帝王学を学び、側用人の間部らが政治面で主導し、家継は追認をする形で、家宣の遺志を継ぎ、幕府を立て直す改革を続けました。
家宣と家綱のもとで新井白石が行った改革は、「正徳の改革」といい、家宣と家綱の治世を「正徳の治」と呼びます。
また、正徳6(1716)年1月、8歳(満6歳)のとき、霊元天皇の3歳の皇女・八十宮吉子内親王と婚約しました。
実は、家継は家宣の存命中から正室天英院の弟・近衛家煕の娘である尚子との婚約が決まっていました。
しかし、天英院と家煕は尚子が家継よりも7歳も年上であることを気にし、尚子を中御門天皇に入内させることで事実上の婚約破棄になっていました。
天英院と月光院は、幼い将軍の立場を強化するために、名付け親でもある上皇の皇女を家継の御台所として迎えようと朝廷に交渉しました。
上皇もこの提案を受け入れて、正式に婚約をすることになりました。
史上初武家へ皇女が降嫁することになったのです。
ところが、残念ながら武家への皇女降嫁は実現せず、14代将軍家茂まで持ちこされることになりました。
早すぎる死

正徳6(1716)年4月30日、家継はたった8歳(満6歳)死去し、増上寺に埋葬されました。
死因は、風邪の悪化による急性肺炎であると考えられています。
これによって、徳川幕府2代将軍秀忠から続く徳川宗家の血統は、断絶することになりました。
徳川家継の墓

家継の墓は、代々徳川将軍家の墓地とされる「三縁山広度院増上寺」にあります。
現在の東京都港区にあります。
昭和33(1958)年から行われた墓所の改葬のとき、歴代将軍の遺骨調査を行いました。
家継の遺骨は保存状態が悪く、長い年月によって散逸もしくは分解され、発見できませんでした。
しかし、残された髪や爪などから、家継はA型だったことが判明しています。
また、愛知県岡崎市にある徳川家の菩提寺・大樹寺には、歴代徳川家当主の墓所と歴代将軍の位牌を安置しています。
この歴代将軍の位牌の大きさは、将軍が亡くなったときの身長と同じだとされています。
それによると、家継の身長は約135cmとされ、8歳にしてはかなり高身長だったと言えます。
徳川家継の母・月光院

月光院は、6代将軍家宣の側室で、7代将軍家継の生母です。
本名は勝田輝子といい、側室としての名前は喜世で、家宣が死去してから月光院と呼ばれるようになります。
宝永元(1704)年、綱豊(後に家宣)の桜田御殿に出仕するようになります。
やがて、喜世は綱豊から寵愛を受け、宝永元(1704)年12月、綱豊は5代将軍綱吉の養嗣として江戸城に入り、正室や側室も一緒に同行しました。
宝永6(1709)年、綱豊は家宣と名を改め、6代将軍に就任します。
この年の7月に、喜世は鍋松(のちの家継)を出産しました。
正徳2(1712)年10月に家宣が死去し、喜世は落飾して月光院と号しました。
翌正徳3(1713)年に家継は将軍に就任し、月光院は従三位の位を賜ります。
家継が将軍になったことで、月光院は大奥で勢力を強め、側用人間部詮房との大奥での振る舞いに対して、周囲は嫌悪感を募らせます。
正徳4(1714)年、江島生島事件が発生します。
江島は月光院の御年寄で右腕とも言える存在、生島は歌舞伎役者生島新五郎のことです。
江島が家宣墓参り代参の帰りに生島新五郎を宴会に招き、大奥の門限に遅れたことから事件が発生しました。
月光院の取り成しで江島は死刑を免れたものの、大奥での権威は失墜、高遠藩預けになり、死ぬまで幽閉されます。
このとき、他にも多くの月光院派が処分されました。
そのため、この一件は月光院の勢力に大きく影響を及ぼし、月光院の影響力は衰えていきます。
正徳6(1716)年、家継は風邪をこじらせて死去しました。
家継の死因の一つとして、月光院が風邪を引いていた家継に無理矢理能楽鑑賞をさせたためとも言われています。
その後、8代将軍として紀州徳川家から吉宗が迎えられました。
延享2(1745)年、吉宗が隠居しようとすると、次期将軍に吉宗の次男・田安宗武を推し、晩年にも影響力を行使しようとしたともいわれています。
吉宗の死を見届けた翌年、宝暦2(1752)年に68歳で亡くなりました。
徳川家継の婚約者・八十宮

正徳4(1714)年8月22日、霊元法皇の第13皇女として生まれます。
正徳5(1715)年9月29日、数え年で2歳のときに、将軍徳川家継との婚約の話が持ち上がります。
当時、夫になる家継もわずか7歳でした。
正徳6(1716)年閏2月18日、納采の儀を済ませ、正式に婚約します。
ところが、2か月後の4月30日に家継が死去したため、初の武家への皇女降嫁と関東下向には至りませんでした。
しかも、本人は数え3歳で未亡人となりました。
この婚約には当時の政治的な思惑が強く反映されています。
当時の大奥では、前将軍家宣の正室天英院と、側室で家継生母の月光院の二大勢力がありました。
一方、京都では吉子内親王の父・霊元法皇と天英院の父・近衛基熙が主導権をめぐり争っていました。
実質政治を行っていた側用人間部詮房や学者の新井白石は、家宣亡きあと、幼い将軍の下で正徳の改革を進めるには、苦しい立場にありました。
そこで、間部らは家継の権威を強化するために、皇女降嫁を提案し、月光院も天英院に対抗する権威を朝廷に求め、皇女降嫁を賛成しました。
また、天英院は家宣存命中に姪の尚子と家継の婚約を進めていましたが、家継と尚子の年齢差を気にかけ、婚約を事実上破談にしていました。
そのため、天英院も正室を皇室から迎えることには前向きでした。
他方、霊元上皇は幕府と対立関係にありましたが、政敵・近衛基熙の権力基盤である幕府との関係に楔を打つため、これに応じました。
近衛基熈はこの婚約に反対しましたが、天英院との関係から表立った反対をしませんでした。
享保17(1732)年8月6日、父の霊元上皇が崩御します。
同年10月29日出家し、法号は浄琳院宮(じょうりんいんのみや)といいます。
宝暦8(1758)年9月22日、45歳で薨去し、墓所は京都府京都市東山区の知恩院にあります。
一説には、出家せずに徳川宗春側室の阿薫となったともいわれています。
まとめ
以上、江戸幕府第7代将軍徳川家継について紹介しました。
4歳で将軍に就任し、8歳で亡くなってしまった史上最年少の将軍ですが、激動の時代を生き抜いていました。
大学卒業後、台湾の台中で1年間のワーホリを経験。
語学を勉強するのが好きで、大学時代に中国語を副専攻で勉強しながら、ラテン語の授業を受けたり、韓国語を独学で勉強したりした。
また、イタリア語をオンラインで学習中。
語学学習の楽しさやさまざまな国の文化を発信。

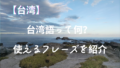

コメント