台湾の七夕節で何をするのかご存じですか。

台湾の七夕はバレンタインデーみたいって聞いたことがあるよ!
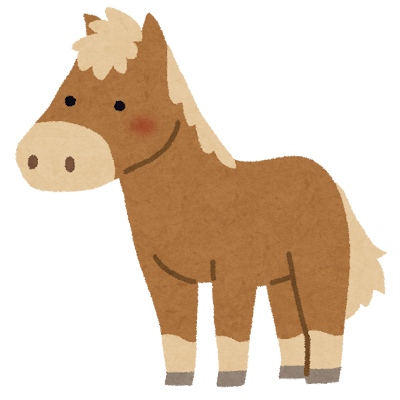
台湾の七夕節について日本との違いを調査してみよう!
この記事では、台湾の七夕節について、また日本の七夕伝説や過ごし方の違いについて紹介します。
2024年今年の七夕節はいつ?

2024年の七夕節は8月10日です。
台湾では旧暦の7月7日が七夕なので、毎年七夕節の月日は変わります。
旧暦と新暦は約1か月ほど差があるため、旧暦の7月7日はだいたい新暦の8月上旬に当たります。

8月なら夏だし雨が降らなさそうでいいね!
日本の七夕は毎年新暦の7月7日で、梅雨の真っただ中のため、毎年七夕の日は雨が降っているイメージがありますよね。
でも、実は台湾でも日本と同じように七夕の日は雨が降るイメージがあります。
8月は真夏ですが、織姫と彦星が一年ぶりに会えたうれし涙で雨が降るといわれています。

日本と同じだね!
中国語で七夕は、「情人節」といい、恋人の日です。
日本では恋人の日といえば、バレンタインデーやクリスマスを思い浮かべますが、台湾ではバレンタインデーはあくまでも近年輸入された西洋の文化という位置づけです。
そのため、バレンタインデーも「情人節」といいますが、七夕と区別するために七夕を「七夕情人節」、バレンタインデーを「西洋情人節」という言い方もします。
台湾の七夕伝説

台湾の七夕伝説は日本に伝わっているお話とかなり違います。
中国語で織姫を「織女」、彦星を「牛郎」といい、意味は「機織りの女性」と「牛飼い」です。
台湾の七夕伝説では、織女は天帝の娘で、牛郎はただの人間です。
登場人物としては、織女と牛郎のほか、牛郎が飼っている老いた牛、天帝、王母です。
王母は織女の母とも天帝の母ともいわれ、立場がはっきりとしません。
基本知識はこれくらいにして、物語を見てみましょう。
長いので、5つの段落に分けました。
むかしむかし、銀河の東側に7人の美しい仙女がおりました。
彼女らは天帝の娘で、「七仙女」と呼ばれていました。
七仙女は手で天空の編んでいて、その中で最も聡明な仙女を「織女」といいました。
彼女はさまざまな美しい雲彩を編み出すことができ、毎日一心一意努力して天を編んでいました。
銀河の外側に一人の牛飼いがおり、牛郎と呼ばれていました。
彼は、両親を早くに亡くし、兄夫婦と一緒に暮らしていましたが、兄夫婦は牛郎に対して冷たく、早く出て行って欲しいと思っていました。
ある日、兄は牛郎に「もうお前も大きくなったのだから、自分で生活しなさい。お前に牛はあげる。俺は家をもらうから出てってくれ」といいました。
牛郎は一頭の老牛と誰も使わない土地を見つけて、そこで仕事を始めました。
何年か経ち、小さな家を建て、一人で生活をできるようになりましたが、傍にいるのは老牛だけ、牛郎は孤独に感じていました。
ある日、ずっと一緒に暮らしていた老牛が、突然牛郎に向かって話しだしました。
「今日の夕方、天の七仙女が銀河で水浴びをする。お前は彼女らが水浴びをしているときに、一番下の服を盗みなさい。その服の持ち主がお前の妻になるべき人だ。」
牛郎は老牛の話を聞くと、口を開けて大変驚きましたが、昼過ぎ、銀河に行き、しばらく待っていると、本当に七人の仙女たちが水浴びを始めました。
その間に牛郎は老牛に言われた通り、織女の服を隠しました。
仙女たちは誰かがこっそり彼女たちの服を隠していることに気が付くと、大変驚き、大慌てで服を着て、飛ぶ鳥のように逃げていきました。
しかし、織女だけは服がないため、水の中にいました。
牛郎は「もし、あなたが私の妻になってくれるのなら、服はお返しします。」と言いました。
織女は恥ずかしく、怒りを覚えましたが、どうしようもないので、仕方なく牛郎の要求をのみました。
結婚後、織女は牛郎がとても真面目に仕事をすることを知り、しかも自分に対してとても優しく気遣いをしてくれたので、ふたりの結婚生活は幸せなものでした。
織女は、牛郎の間に男女の双子をもうけました。
10年が経ちました。
人間界の10年は、天界の10日で、天帝はやっと織女が牛郎に嫁いでいることを知り、織女を連れて帰るように王母に命令します。
織女が連れて行かれた後、牛郎は子どもたちと銀河に行きますが、銀河はすでに王母によって天まで昇ってしまい、普通の人はそこに行く術がありませんでした。
牛郎と子どもたちが家に帰り、泣いていると、老牛がまた口を開きました。
「牛郎、悲しむことはない。私はもうすぐ死ぬ。死んだ後、私の皮を剥いでそれを羽織ると、体が浮いて天に行くことができる。」
老牛はそう言い終えるとすぐに、倒れて動かなくないました。
牛郎は老牛の皮を羽織ると、本当に体が浮いて、天に行くことができました。
牛郎と子どもたちが銀河に着くと、王母はすぐに銀河を大海のように変えて、彼らは渡ることができないようにしました。
牛郎はどうしたらいいかわからず、子どもたちと一緒に柄杓で川の水をすくい、川を枯れさせようとしました。
三人が必死に毎日毎日手を休めずに、水をすくい続けるので、天帝はその姿に感動し、彼らに一年に一回会わせることを約束しました。
それ以降、毎年旧暦の7月7日に、鵲(カササギ)が銀河の上と飛び、橋を架け、織女と牛郎が会えるようにします。
毎年たったの1回しか会えないため、織女はいつも泣いて喜び、その涙が落ちて、人間界はいつも雨なのです。
なんと台湾のお話では、牛郎と暮らしている老いた牛が話し始めます。
この老牛は、もともと天に住んでいた神ですが、悪い事をして牛に変えられてしまったそうです。
しかも、老牛に言われたように牛郎は織女の服を隠し、脅迫する形で2人の結婚生活が始まります。

信じられない!!これのどこがロマンチックなの!?
台湾人にとっても当然牛郎の行為は許せないものですが、このような仙女と人間の男の話がたくさんある中で、七夕伝説だけ相思相愛になり、仙女は人間界に残って人間の男と一緒に暮らすという選択をします。
そこが七夕伝説がロマンチックだといわれる所以です。
実際、日本にも天女のお話は各地にありますが、いずれの天女もみな羽衣を見つけ次第天に帰ってしまいます。
日本の七夕伝説は韓国と同じなので、恐らく韓国に伝えられた時点、もしくは韓国に伝わったときにお話しが変わって、日本に伝わったのでしょう。
そのため、台湾と日本では全く違う七夕伝説があるのです。
ちなみに、中国語でホストのことを「牛郎」といいます。
やはり彦星もホストも悪い男という印象があるのでしょうか。
台湾の七夕の過ごし方

台湾の七夕は、「恋人の日」と言われるため、恋人と一緒に過ごしたり、プレゼントを贈り合ったりします。
台湾の七夕は、今では「恋人の日」という印象が強いですが、元々は台湾の七夕は子どもの健康と成長を願う日でした。
そのため、子どもの健康や成長を願うための風習がいくつかあります。
台湾の七夕伝説では、密かに織女と牛郎の子どもを織女のお姉さんたちが育てたというエピソードがあり、織女を含む7姉妹(七仙女)は 「子どもの守り神」と呼ばれます。
そして、幼い子どもがいる家庭では、香炉や花、果物を持って、織女を祀る廟に行きます。
廟では、古い貨幣などを赤い糸を通して繋いだ「絭(ケン)」というお守りを幼児の首にかけ、子どもが無事16歳(昔の成人年齢)を迎えることができるよう健康と成長を願います。
そして、16歳になった年の七夕に「絭(ケン)」を外し、麺やちまきなどを織女にお供えし、無事に成長したことを感謝するという風習がありました。
また、ほかには「月下老人」という恋愛の神様のところにお参りに行くことも台湾の七夕の風習です。
「月下老人」は恋愛の神様なので、七夕のときに良縁を求めお参りに行くと一年の中で一番効果があるといわれています。
ぜひ、みなさんも月下老人の廟にお参りに行ってみましょう。
まとめ
以上、台湾の七夕節や七夕伝説、七夕節の過ごし方についてまとめました。

台湾の七夕伝説が衝撃過ぎた!!
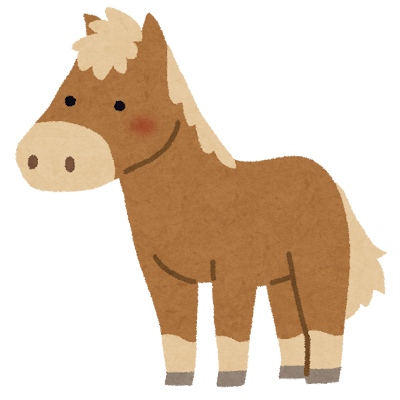
日本人的にはあまりロマンチックに感じなかったなあ
日本とは全く違うお話に驚いた方も多いかと思いますが、日本と違うのでとても興味深いですね。
七夕の時期に台湾に滞在する方は、台湾人のように七夕を楽しみましょう。
大学卒業後、台湾の台中で1年間のワーホリを経験。
語学を勉強するのが好きで、大学時代に中国語を副専攻で勉強しながら、ラテン語の授業を受けたり、韓国語を独学で勉強したりした。
また、イタリア語をオンラインで学習中。
語学学習の楽しさやさまざまな国の文化を発信。
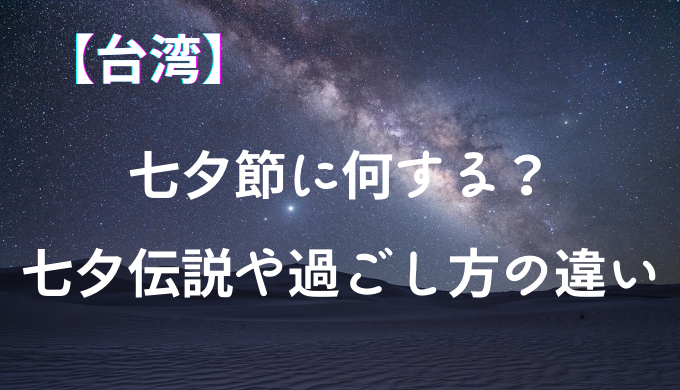

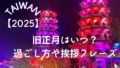
コメント